ホーム » 合格するブログ » 合格する現代文
共通テスト対策「正答率9割」を勝ち取る方法とは?
問題文および選択肢の言葉のうち、重要な言葉はどれなのか? が洞察でできるようになれば、正答率9割に達します。例えば、「生徒と教師の会話」の中に空欄X、Y、Zと抜かれている問題がありますが、それは空欄前後の指示代名詞や接続詞をもとに問題設計がなされます。したがって、XYZの前後にある接続詞や指示代名詞が太字で浮かび上がってくるように読めるようになれば、正答率9割に達します。
もちろん、選択肢の中にも浮かび上がってこなくてはならない言葉があります。要するに、どの言葉を読むのか、というのが共通テストの国語においては、非常に重要です。
聞くところによると、音楽の楽譜の読み方も同じらしいです。長い曲ですと、ものすごく分厚い楽譜になります。その中の無数の音符のうち、どの音符に意識を向ければ、聞いてる人の心を宇宙に飛ばすことができるのか。その音符を見つけるのがうまいのが、例えばバーンスタインとか小澤征爾さんとか佐渡裕さんなのだそうです。そういった話を聞いたことがあります。
共通テストの国語もまったく同じです。冗長としか言いようのない問題文の中の、どの言葉が太字で浮かび上がってくるように読めるようになればよいのか。それを頭で理解するのではなく、体に覚えこませること。これが正答率9割を勝ち取る方法です。要するに、どの言葉を読むのか、です。

共通テスト国語で正答率9割を達成する方法とは?
例えば、現代文の場合だと、傍線部とはどういうことか? 答えよ、とか、傍線部の理由について答えよ、という問題があります。傍線部とはどういうことか、というのは、傍線部を言い換えている選択肢として最も適切なものを選べ、ということですから、まず解答の根拠となる本文の範囲を特定します。
なんとなく特定するのではありません。傍線部を含む文章と、その前後の文章の関係を言えなくてはなりません。それが言えるようになると、おのずと解答の根拠となる問題文の範囲を特定できるようになるかと思えば、実は共通テストはそこからさらに一手間加えろと言っています!
例えば、傍線部の前後に指示代名詞がある場合は、その指示代名詞が指し示すものをとらなくてはなりません。
そのようにしてようやく、解答の根拠となる範囲が特定されます。
次に、選択肢①から⑤を順番に消していかなくてはなりません。選択肢は読点のところで区切って吟味します。主に解答の根拠となる本文の範囲に書いてある/書いていない、を基準に選択肢を消していきますが、ここで大事なのは、△を積極的に打つことです。
皆さん、〇か×かのどちらかを打とうとするから、時間がかかりすぎて時間切れになるのです。△を積極的に打つことです。選択肢のための選択肢、要するにダミーの選択肢だっていくつも用意されているわけですから、そんなものいくら検討しても「よく分からない」としか言えないからです。
など、設問ごとに解法テクニックが必ず存在します。なぜなら、50万人ほどが受験するのが共通テストですから、誰が聞いても納得のいく解答の根拠が存在しなく「てはならない」からです。 50万人全員が聞いて納得する解答の根拠は1つです。文法です。AだからBゆえにCという論法にもとづいて共通テストの問題は作成されています。
そこから逆算して解法を導けばよいのです。古文漢文もまったく同じです。大問3の図表の読み取り問題もまったく同じです。
ということなわけですが、高校生がひとりで作問意図から逆算して解法を導き出すことができるのかといえば、ほとんどの高校生は一人ではできないだろうと私は思います。
また、私のもとには駅前の塾で3年間共通テスト対策をやったけどどうしてもスコアが7割から伸びない、という生徒さんが今年も何人もいらっしゃいました。毎年思うことですが、作問意図から逆算して解法を説明できる先生が少ないのだろうと思います。進学校であっても、学校の共通テスト対策の授業は、問題を解かせたのち「解説を先生が読み上げる」のだそうです。それでは正答率が伸びなくて当然です。そんな甘いものじゃあないのです。共通テストは。
共通テスト国語で正答率9割を達成しようと思えば、作問意図から逆算して解法テクニックを教えてくれる先生に教わるのが近道です。

【高校生】現代文の勉強法
他方、受験国語は、大学教育を受けるに値するスキルを持っているか否かを問うなかなか底の深い問題が出されます。したがって、勉強法は以下の3点に絞られます。
1,問題文の構造を洞察する
国語の成績が安定しない理由は問題文の構造を洞察できていないからです。文章は構造をもっています。その構造は問題文の最初の1文字から最後の1文字にいたるまですべてに貫かれています。途中途中で何を言っているのかが分からなくなっても、構造にしがみついて読解する限りにおいて、迷子にはなりません。文章とはそのようにして読むものです。
2,構造に依拠して論の流れをとる
構造をとるスキルが身につけば、次にその構造に依拠して論の流れをとる訓練をします。高校生が「現代文が読めない」というのは、その目に見えない「流れ」を読めていないからにほかなりません。段落ごとに要約の練習をしてもよくわからない、というのは、流れを意識して要約していないからです。誰かいい先生に教わる必要があります。
3,選択肢を消すテクニックを身につける
模試や入試には作問意図があります。その意図から「逆算して」選択肢を消すテクニックを導き、それを体に染み込ませます。作問意図は学校で教えてくれないことの代表格でしょう。誰かいい先生に教わる必要があります。
※ちなみに記述問題対策は、問題文から言い換え表現と反対表現をとりつつ、著者の主張をとる練習をします。そしてそれらを「余計な接続詞を使うことなく」文章化する訓練をします。
以上が高校生がやるべき現代文の勉強です。

共通テスト国語、正答率9割2名、8割4名の秘訣とは?
ちなみに、マナリンクの講座と人見読解塾の講座は同じ内容です。価格は・・・・・人見読解塾は5週目の授業は無料であり、かつ入塾金がないので、人見読解塾の方が安いです。授業料自体は同じ金額(60分8,800円)です。私が煩雑な事務処理が苦手なので5週目無料、入塾料なしにしています。シンプルイズベスト。

合格する私大対策|3つのポイント
01:まず過去問を解く
当たり前ですが、まずは過去問を解きましょう。赤本を買ってないと言い放った受験生がいたので、あえてこんな当たり前のことを書きました。赤本には過去問とその他の情報が載っていますが、それらをすみずみまで読み解くのです。受験は情報戦です。
02:作問意図を洞察する
これは高校生ひとりでできないかもしれません。みなさんこれまで問題を解く力をつけてこられたはずです。その力を全方位的に、すなわち気合いで出し切ろうとしても限界があるどころか、それでは桜が咲かなかったりします。受験問題はどこまでいってもそれをつくった人の意図に正確に応えられているか、という、いわば「いい子」の側面が必要です。作問意図から逆算して自分なりに解法を会得することがなにより重要です。
03:因果関係、逆接
作問意図を洞察できれば即座にわかることですが、現代文も古文も、問題文にある因果関係をあらわす接続詞か、逆接をあらわす接続詞に着目させたうえで問題を解かせることが多いものです。したがって、それらの接続詞に着目しながら論の流れ(話の流れ)を掴む読み方を「体得」してください。共通テストのような情報処理問題ではなく、本来的な読解力を試す私大の問題はそのように解きます。
私大の問題は相性によって解けたり解けなかったりします。偏差値低めの滑り止めの大学だからまあ大丈夫だろう、ではちょっとマズイ。早稲田対策をしている受験生が滑り止めの偏差値50ちょっとの大学の過去問の正答率が低いなんてことは、ふつうにあることです。「問われ方」に慣れていないから正答率が低くなります。
的を射た過去問演習をとおして、どうか行きたい大学に行ってください。

共通テスト直前に気をつけるべきこと
というわけで、以下に気を付けるべき点についてお話申し上げますので、ぜひ参考になさってください。
1,見たことのない問題への対処法
見たことがない問題が出ても決してあわてないことです。まず、
①問いが何を問うているのかを理解する、洞察することが重要です
共通テストはおかしな問い方をしてきますので、問いが実は何を問うているのかを理解する必要があります。それが手順1です。20秒ほどでできるでしょう。理解した結果、単純に傍線部の言い換え表現としてふさわしい選択肢をとってくれと言っているとか、比較的ありふれた結論に落ち着くのが常です。
②これまで勉強してきた解法テクニックで解けないか検証してみる
これは少々時間がかかるかもしれません。しかし、それしか方法がないのであれば、そうするしかありません。さもなくば保留にして次の問題に移るか。
2,残った二つの選択肢を比較検討すること
5つの選択肢を2つに絞れた場合、残った2つの選択肢を順番に読むのではありません。2つの選択肢を横に並べて比較検討することでしか消せない設計になっている問題が多々あるからです。共通テストの選択肢は、「なぜ③の選択肢が正解なのか」と問われても、残ったもう1つの選択肢と「比較検討した結果」、③の方がよりホワイトに近いからだとしか言えない選択肢を作ってきます。したがって1つの選択肢を穴があくほど読んだところで答えは出ないと肝に銘じてください。
3,判断がつかない選択肢を保留にする勇気を持つ
〇か×か判断がつかない選択肢をいつまでも、本文を読み返しながら検討するから、時間切れになります。 1分ほど考えて判断がつかない選択肢は即座に△を打って保留にする勇気を持ちましょう。共通テストの思惑にハマってはいけません。
4,空欄XYZは文法に気をつける
空欄Xの後に「すなわち」があれば、空欄Xは「すなわち」の後の文章の言い換え表現としてふさわしい選択肢をとってくれといっています。空欄XYZはXYZの前後にある文法に依拠して解かせることが多いのです。また、指示代名詞が周辺に存在する場合は必ず、指示代名詞が指し示すものをとってください。それをとらずに雰囲気でやってしまうから間違えるのです。
などなど、共通テスト直前に気をつけるべき点を挙げようと思えばいくらでも挙がりますが要するに大切なことは、選択肢を比較検討することです。
つまり、明日は国語の問題を解きに行くのではなく、選択肢を比較検討しに行くのです。1つの選択肢だけを吟味検討しようとすれば、論点が明確になりづらいので、その必然の結果頭がぼんやりするはずです。しかし、2つの選択肢を比較検討する場合は、2つあるわけですから論点が明確になります。論点が明確なことに関しては、多少緊張していても正常に頭が働いて検討できるでしょう。
皆さんの健闘を祈ります!!

【共通テスト国語】選択肢を完全攻略する方法 ~作問意図から逆算したら言えること~
すなわち、選択肢は絶対評価ではなく相対評価で選ぶ。そういった情報処理能力を試されているのが、共通テストの国語の選択肢です。したがって、以下のような手順で選びます。
1,5つある選択肢のうち、まず3つを消す
3つは簡単に消せます。本文に書いてあるか書いていないか、すなわち目に見えている文字列をそれと読めているか。自分の思い込みで好き勝手に読んでいないか、が試されています。
2,残った2つの選択肢を読み比べる
残った2つの選択肢のうちの1つを選んでいつも間違うというのは、読み比べることができていないからです。必ず残った選択肢2つをちゃんと読み比べて、その違いをとります。違いが分かれば、何を検討すべきか、すなわち論点がおのずと浮かび上がります。その論点をもとに、本文のしかるべき箇所を読み返して1つに特定します。
3,それでも消せない選択肢は?
選択肢の句読点のところですべてスラッシュを入れます。1つの選択肢が3つに区切られたら、選択肢2つで合計6ヶ所検討する箇所が生まれます。ここからは過去問演習を繰り返さないとよくわからないことですが、共テ特有の選択肢の作られ方というものがあります。例えば、比較の表現の箇所、あるいは因果関係を取っている箇所は、本文には比較の表現がなかったりします。あるいは、本文はそんな因果関係を述べていなかったりします。あるいは、本文に書かれてある文字列ではあるものの、本文では違うことについて述べられている箇所だったりします。そういったものを消していきます。
4,注意すべき点
〇〇について筆者が述べていることのうち最も適当なものを選べ、という問題における選択肢で、明らかに本文に書かれてあることを書いてあるという理由で消しづらいことがあります。よく本文を読み返してみると、〇〇について書かれている箇所ではなく××について書かれてある箇所だったりします。そういうのはちゃんと読んで消しましょう。
5,傍線部内あるいは傍線部の前後に指示代名詞が含まれる場合
その指示代名詞が指し示すものを明らかにすれば、自ずと選択肢が1つに絞られてきます。
他にもいくつかのテクニックはありますが、大体以上のような感じです。
受験生がまずやるべきことは、選択肢の相対評価のやり方を体得することです。これは共テ特有の情報処理能力といってもいいでしょうから、過去問演習を繰り返すしかありません。
総じて、共通テストの国語の選択肢問題は相対評価にもとづいて情報処理をさせる能力か、文法に依拠して問題文を書かれてあるとおりに読む能力かの、いずれかの能力しか問うていない。そういった底の浅い問題だと言えます。
したがって、残った2つの選択肢を1つずつ穴があくほど吟味するとか、1つずつ解答の根拠を本文に求めるとか、著者の主張をかみ砕いて理解するなどといった勉強法をいくら繰り返しても、得点は上がりません。そういうのは中堅以上の私大入試問題か、国公立の2次試験問題でやりましょう。早稲田や神戸大の問題はかなり秀逸です。勉強になります。
特に早稲田を受ける方で170点以上のスコアがでない方は、そういった勉強にはまっています。すなわち、共通テストの罠にはまっています。
即座に勉強法を変えるべきでしょう。

大学受験現代文の正しい勉強法「正しくつまずくということ」
参考書って、かなりこと細かに詳しく書かれています。しかし、指示代名詞が指し示すものを自力でとれるようにならないと、真に読めるようになりません。なぜなら、大学受験問題における傍線はしばしば、指示代名詞の周辺、あるいは指示代名詞を含むように引かれるからです。そこを「自明のもの」としてさらっとやってしまうと現代文の力がつかない。早稲田大学を受験するような高校生であっても、「これ」とか「それ」が指し示すものを厳密にとらず、雰囲気で読んでいることが多い。だから選択肢問題が解けないのです。
多くの高校生は、つまずくことを良くないことと思っています。授業をしていれば、そのことがよく分かります。しかし、現代文の正しい勉強法というのは、つまずくべきところに正しくつまずくことでしかないのです。著者は、あるいは作問者は、つまずいてほしいから、あえて「そのように」本文を書くのです。そのような問題を作るのです。
正しくつまずくことによって、 3分でも5分でもいいので、ちゃんと立ち止まって、それが何なのかを特定する。例えば「これ」「それ」という指示代名詞が何を指し示しているのかを特定する。英語であれば、何と何を結ぶandなのかを特定する。そんなふうに正しくつまずきながら読む練習をしないから、いつまでたっても読めるようにならないのです。私は哲学書をつまずきまくって、ようやっと読めるようになりました。高校生にとっては、シブいおじさま先生がお書きになった論説文の問題文が、私にとっての哲学書に相当するはずです。
ちなみに、参考書は正しくつまずくようにできていません。なぜなら、つまずかないように解説してくれているからです。だから、参考書ルートで現代文の勉強をするのには限界があるのです。

共通テストの小説問題の正答率を上げる方法
共通テストの小説問題は「文法問題」であり、「蓋然性の高い選択肢を選ぶゲーム」です。まあ、なんと言いましょうか、そんなことをするから小説を読まない人が増えるのです。本来小説は精神分析のよき書であり、象徴ごっこを楽しむ豊かな言葉の世界なわけですが。それはさておき。
文法処理のしかた
問題文において因果関係が結ばれていない箇所を、選択肢においては因果関係を使って書かれていないか? などをチェックしていきます。あるいは、原因と結果が逆ではないか? と疑いながら選択肢を読みます。
蓋然性の高い選択肢を選ぶテクニック
まず選択肢を横に読みます。すなわち①~⑤すべてをざっと読みます。すると5つの選択肢から「本文のどこを吟味してほしいのか」が見えてきます。つまり作問者の意図が見えてきます。その本文の箇所を再度丁寧に読むことで正解の選択肢1つにたどり着けます。
小説問題に限らず共通テストの国語は、正解を1つにする必要があるので、おのずと上記2つの解法で解く問題になっています(ならざるをえなくなっています)。それを「論理的思考」を磨くことで解こう! なんていう先生がいますが、ちょっとどうなのかなと思います。そうではなくて、文法に依拠したただのゲームです。さあ、ゲームを攻略しよう!

大学入試対策における現代文の「参考書ルート」ってなに?「真の勉強法」ってなに?
参考書ルートとは?
自分に合った参考書を適切な順番で勉強すれば志望校に合格できる。その前提のもと、自分に合った適切な参考書で勉強することを、最近は「参考書ルート」と呼んでいるそうです。
参考書ルートの問題点
たしかに、自分に合った参考書で勉強すれば合格は近づくのだろうと思います。
しかし、現代文は――じつは現代文に限らず「読む」と「書く」の教科、すなわち古文、漢文、英語、小論文は、参考書「ではなく」問題集を解く必要があります。
具体的には、参考書が「こう問われたらこう解答せよ」みたいなことを教えてくれるので、その知識をもとに、実際に言葉の大海に出て問題を解く。これが「絶対条件」です。
私のもとには、参考書ルートで勉強した「現代文を読めない生徒」が毎月訪れます。
論説文を実際に読むことなく、参考書で方法論だけを学んだのですから、読めなくて当然です。
「参考書1冊仕上げたのですが、次なにをすればいいですか?」と問うてくる生徒もいます。
「実際に問題を解こうよ。きみ、たぶん解けないと思うよ」
で、実際に解けません。
ほらね。
そこから授業がはじまります。問題文のどこをどう読むのか? どのように選択肢を消すのか? すべて「アナログで」教えます。「読む」時の脳内はアナログ的に、すなわち推論で情報処理されているのです。
参考書は道具。道具を実際に使って「読む」のが真の勉強
多くの人が誤解していますが、参考書は読解の方法論を教えてくれる道具です。
その道具を使って「実際に読むから」読めるようになるのです。現代文の参考書なんて、ポイントとなることをそうたくさん書いてあるわけではないのだから、3日で参考書を読んで、あとは演習、演習、演習。
で、解き間違えた問題は「どう思考すれば正解にたどりつくのか」を、先生と徹底的に(ときに議論になってもいいので)納得し、頭にたたきこむ。正解にたどりつく思考ルートを脳内にすり込む。これが現代文の真の勉強です。
現代文はちょっと苦痛だがしかし
読むのは、最初、苦痛を伴うと思います。その苦痛を避けるために参考書ルートに走る生徒が多い。しかし、いつの時代も「読む」と「書く」は、苦痛を感じつつ始めるしかないのです。
やがて苦痛が快感に変われば合格安全圏に入っています。
時代が変わっても勉強の本質は不変です。
教育産業は新しい言葉を流行らせます。そうしないと儲からないから。勉強法が分からず困っている生徒や保護者がそれに飛びつきます。
やがて私のもとに「参考書ルートで勉強しても国語の成績が上がらないのですが」とやってきます。
私は金儲けが得意ではないということもありますが、参考書ルートという言葉を得意げに話す生徒を見るたびに「なんだかなあ」と思います。
宣伝ちっくですみません
なぜ私が上記のようなことを言うのかといえば、勉強というのは生徒さんと教員で汗を流しながら1つずつ積み上げていくものだと思っているからです。それが真の勉強だと、私が考えているからです。
汗もかかず、きれいなワイシャツを着て、生徒さんに「コンサル」をし「こういった参考書がおすすめです」と、折り目もついていない参考書を差し出すことが誠実さだと、私は全く思えないのです。
無論、「そのレベル」ができない生徒さんがいるから、コンサル系の塾に需要があるのだと思います。しかし、これは実際にあった話ですが、同志社大学に合格する学力をお持ちの方であっても、参考書ルートでは勉強に限界があります。
例えば、古文の参考書には、大学受験の古文問題の解き方が非常によく書かれています。しかし、書かれてあることを実際に運用できるかどうか、使えるかどうかというのはまた別の話です。なぜなら、古文読解は参考書に載っている情報を使って推論するから解読できるのであって、推論の力がないと、せっかく参考書で得た情報は宝の持ち腐れにしかならないのです。
おわりに
参考書には、書ける情報に限りがあります。これは、その参考書の著者の頭が悪いとか、そういった話では全くなく、言葉が持つ限界です。
言葉は静的なものを静的に記述するツールです。他方、推論というのは頭の中の運動です。静的言語で動的運動を記述できるのか? 平泳ぎの方法が書かれた参考書を読むと平泳ぎができるようになるのか?
そういった問題と全く同じ性質を持つのが参考書ルートの問題点であり、その問題点を克服する方法、すなわち生徒さんと一緒に汗をかきながら脳内運動をすることが、私にとって真の勉強法です。

共通テスト(現代文)のからくりが分かれば30点UPします
共通テストの問題文は一読すれば「何を言っているのか」が理解できる程度の平易なものです。したがって、高校生の課題はおのずと、選択肢選びに絞られます。5つの選択肢のうち3つ消して2つ残れば、その2つの選択肢の違いを探し出します。
その際に知っておくべきことは、「選択肢は問題文の『ある言葉』の言い換え表現で作られている」という事実です。
高校生に言い換え表現をとらせるのは、たとえば、神戸大学の二次試験。非常に秀逸な問題、良問です。そこまで秀逸ではないものの、しかし共通テストも同じです。選択肢に含まれている「この言葉」はじつは、問題文にある「あの言葉」の言い換え表現なのです。
それを洞察できるようになれば、正答率はうんと上がります。
ただし、言い換え表現は「あとからそれとわかる」ものだったりします。つまり「明らかにそれと分かる」ようには言い換えていない。このへんが共通テストのいやらしいところです。
だから、消去法なのです。
つまり、①~⑤の選択肢は、(1)ブラック(2)グレーブラック(3)グレーホワイト(4)ホワイトという、いわばグラデーションのように構成されています。そしてしばしば、ブラックの選択肢は存在しません。
したがって、結果的に、グレーホワイトの選択肢が2つ残ります。
そしたら次になにをやればよいのか。
残った2つの選択肢の異同をとります。そのうちの違うところをもとに、本文のしかるべき箇所を読み返し、正解を1つに絞るのです。絞ったときに「?」と思わないことも重要です。なぜなら、その選択肢はグレーホワイト、すなわち正解といえば正解(だが、ほかにもっと選択肢の作りようがあるだろう)というような選択肢で「しか」ないからです。
というようなことをやれば、共通テストの現代文はあっという間に30点UPします。なぜなら、1問あたりの配点が高いからです。

関関同立・マーチに合格する現代文の勉強法 |神戸大学(2021年度)の過去問をもとに
関関同立を受験する生徒さんの中には、例えば神戸大学の滑り止めとして受験する人がいます。大阪大学や京都大学の滑り止めとして受験する生徒もいます。
したがって、ある一定レベル以上の学力を担保していないと、関関同立の合格安全圏に入ることは難しいのが実情です。
さて、今回は、「関関同立に合格するための現代文の勉強法」について、神戸大学の過去問(2021年度)の大問1をもとに解説したいと思います。
「国公立は受験しないから自分には関係ない」と考えてはいけません。それでは、合格安全圏に入れません。
さっそく見ていきましょう。
著者の主張がどこに書いてあるかくらいはわかりますよね?
問題文を一読して何がわかるのかと言えば、最終段落に著者の主張のようなものが書かれてるな、ということだけではないでしょうか。
例えば、最終段落の冒頭、
認知における未来志向性を、効果における未来志向性と混同しないことが重要である。
ここは明らかに著者の主張ですが、「で? それは何を言っているのだ?」がわからないと、問題を解くことはできません。
言い換え表現と反対表現を問題文に求める
では、どのようにすればわかるのか? といえば、問題文の中から言い換え表現と反対表現を取ることによってわかります。
なので、以下に取ります。
1段落目を読んで「哲学(者)」と「科学(脳研究)」が対立構造をとっていると洞察できる高校生は少ないでしょう。
なので、2段落目以降を粘り強く読むしかありません。
そうするとわかることは、例えば、
非難に値する⇔修正可能
後ろ向き⇔前向き
倫理⇔科学=イーグルマン=遺伝と環境
過去志向⇔未来志向
タイプ⇔トークン
というような対立構造と言い換え表現が取れます。
縦の列も「=」表現です。
すなわち「非難に値する=後ろ向き=倫理=過去志向・・・・」ということ。
著者の主張をどう理解する?
倫理と科学をそれぞれ検討をしなくてはならないと言っています。さらには、倫理なしに科学だけを妄信する、そんな人間のあり方が可能なのか? と疑問を投げかけています。
その背景には、昨今の倫理を軽視する社会に警鐘を鳴らしたいという著者の願望が透けて見えますが、おそらくそこまで読み解くと記述解答で減点を食らうと思います。
が、しかし、著者は倫理が重要なのか、科学が重要なのか、どう考えている? と問われたら、「どちらも重要だけれど、軸足は倫理に置くべきではないか」と言っているというのが分かるでしょう。
合格する人がひそかに持っている能力とは
私はつねづね「文章の<構造>を読み解けないと関関同立やMARCHに落ちる」と言い続けていますが、構造をとるとはこのようなことです。
つまり、構造をとることによって、文字列として目に見えている著者の主張が「じつはどういうことか=何を言っているのか」が見えてくるのです。
ちなみに、2023年度の青山学院大学の過去問の大問1は、そこまで精緻に反対表現と言い換え表現を取れなくても問題が解けるようになっています。
が、しかし、反対表現と言い換え表現を精緻に取る能力がないと、得点は安定しないでしょう。
関関同立に合格する現代文の勉強法
何度もしつこく言いますが、合格できる人は推論の能力をじつは持っています。どれだけ勉強していないように見えようと、チャラチャラしてるように見えようと、推論する能力を、じつはひそかに脳内に持っているのです。他人からは見えないだけで。
というわけで、関関同立やマーチに合格する現代文の勉強法は、問題文の中から言い換え表現と反対表現をとる、すなわち問題文の構造を読み解く訓練をするというものです。
ちなみに、国語のセンスがある人はそのような勉強をしなくていいのではないかとお考えになる方もいらっしゃると思います。しかし、私が長年生徒さんを見てきた中で言えることは、センスのある人は自分にとって苦手なジャンルの論説文が出題されたらスコアが大きく下がるということです。
つまり、センスというのは、「ある」傾向を持つ文章において適用される何らか生まれ持った素晴らしい能力であり、「どのような」文章においても適用される能力では決してないということです。
これは世界のプロを見ても明らかでしょう。
例えば、私はクラシック音楽が好きなのでさまざまな音楽会に行きますが、世界的指揮者だって時には、ぱっとしない演奏会をしてしまうものなのです。そこには、もしかすればその日の指揮者の体調の悪さがあったり、あるいは本番直前に奥さんと喧嘩したというようなことがあったりするのかもしれません。あるいは、練習の時にオーケストラと険悪な雰囲気になってしまったというようなことがあるのかもしれません。
しかし、指揮者だって人の子ですから、どれだけ音楽的センスに恵まれているといっても、自分が得意な音楽と不得意な音楽があるはずです。ベートーベンの音楽はものすごく得意だけど、ハイドンは何回指揮してもおもしろみを感じないといったような。
というわけで、長くなるのでこのへんでやめておきますが、問題文の構造を読み解く力、すなわち構造読解能力をつけるというのが、関関同立やマーチに合格する現代文の勉強法です。

参考書ルートにおける3つの限界と本当の勉強法
参考書ルートの問題点は3つあります。
1つは、参考書や解説書に物理的に記載できない情報をどのように得るのかということ。
2つ目は、たとえ記載があっても「なぜそう言えるのか」が自力でわからないという点。
3つ目は、参考書で知識を得ることと、実際にその知識を使って問題を解くことはまったく違う能力だということです。
以下に順番に解説します。
01:参考書に記載できない情報がある
参考書や問題集の解説書というものは最初にページ数を決めてから作られます。したがって、既定のページ数に文字を納めなくてはいけないので、当然のように、自明のこと(参考書の著者が自明と思っていること)は書かれません。あるいは、本当は書きたいのだが紙幅の関係で書けないことが必ず生じます。
例えば、古文であれば、参考書や解説書にある模範訳には、その文章の主語が書かれています。しかし、それを読んだ高校生は「なぜこの文章の主語は光源氏になるのだろう?」と思います。参考書や解説書に尋ねてもどこにも書いていません。
要するに参考書というものは、不完全なものですから、参考書ルートというのは不完全なものを土台にしている勉強法のことです。完全なものにしようと思えば、家庭教師を雇ってマンツーマンでわかるまで教わるしかありません。それが1つの参考書の限界です。静的なことしか記述できないという言葉の特性がもたらす限界と言えるでしょう。
02:「なぜ」が自力でわからない
「AはBである」という参考書の解説を読んで「ふーん、そうなんだ」としか思わないから大学受験に失敗するのです。これは断言します。特に現代文や古文、英語の場合、「なぜそうなるのか」を言えないと確実に落ちます。
言えないというのは、表面的に勉強してるふりをしているからであって、真の勉強ではないからです。
なぜその解釈(訳)になるのか? がわかることを勉強と言います。
03:知識を得ることと知識を運用することは全く別
参考書ルートを標榜している塾や学習塾がやってるのは、いわば勉強のコーチングです。あなたはこの能力が足りていないから、この参考書を使って勉強すれば能力が補充されます、というコーチングをしているだけです。
そのことによって、運が良ければ、知識が補充されます。しかし、そこで満足するから志望校に落ちるのです。
実際の勉強は、参考書ルートで得た知識をどう使うか? すなわち「どう=方法」を「体得」するところにありますから、参考書ルートで知識を得たというのは、勉強のスタートラインに立ったにすぎません。
例えば、参考書を読んで関係代名詞節とはどのようなものかが分かった場合、その知識を実際に長文読解演習を使って運用するのです。
すると、おそらく、和訳できないでしょう。
関係代名詞節の始まりは理解できても、どこまでが関係代名詞節なのかわからなかったりするでしょう。
そういう「実際的な読み方」というのは、実際に手取り足取り家庭教師と一緒にやっていかないと身につかないものです。
知識があるから合格できるのではない
知識があればどうにかなるという「知識至上主義」が幅を利かせている昨今ですが、勉強というものは、実際に泥臭く読む、書く。これに尽きるのです。それを「昭和の根性論」といって遠ざけるから、「勉強法がわからない」と言うのです。勉強法をあなたはすでに知っています。しかし、「その選択肢はイヤだ」と言って見ないふりをしているだけです。だから落ちるのです。
つまり勉強とは、「知識」という「静的なもの」を頭に詰め込むことではなく、それを実際に使う「運動」なのです。関関同立やMARCH以上の私大や、おおむね神戸大学以上の国公立大学はその「脳の運動能力」のいい生徒さんにだけ合格通知を贈っているのです。
私は長年、泥臭い授業をしていますので「参考書ルート」という言葉が流行っている世の中を上のほうから眺めていますが、「コンサル」にのみ高校生たちが高いお月謝を払うのもどうなのかなと思ったりします。
本当の勉強法
というわけで、もうお気づきの読者もいらっしゃると思いますが、本当の勉強法というのは、1つずつ思考を積み重ねていくというものです。思考というのは推論する能力のことです。
例えば、中堅どころの中高一貫校にお通いの生徒さんで地頭はいいのに模試の点数が低い生徒さんがいました。英単語やイディオム、古文の重要古語などをよく覚えている素晴らしい生徒さんでしたが、どうしても模試で点数が取れない。学校の授業を真面目に聞いても取れない。
ということで、私のもとに来られました。私は即座に推論の力を養うための授業を行いました。現代文であれば、本文の中から言い換え表現と反対表現を取る。そのことによって著者の主張を導き出す。その上で、選択肢のどこが違うのかを特定する。それだけの訓練で30点、模試の点数が上がりました。
英語であれば、1文ずつは読めるわけですから、今読んでいる文章と前の文章の関係を言えるようにする。そのことによって段落として何を言ってるのかを理解する。その上で、段落と段落の関係を取る。その結果、問題文全体としてどのように論が流れているのかを理解する。そのことによって、選択肢を正確に消すことができるようになる。あるいは、下線部和訳であれば、文章の構造を壊さないようにしつつ、直訳ではなく、問題文の内容を理解しているということを採点者にアピールできるような日本語文が書ける。そういった地点まで成長しました。
推論というのは脳内の運動ですから、参考書に非常に書きづらいものなので、書かれていないのです。また、学校の先生の中には、推論の重要さにおそらくは気づいておられない方が多いのだろうと思います。
関関同立やマーチクラス以上の大学、あるいは国公立であれば神戸大学以上の大学というのは、「考える力」を入試で試します。その「考える力」というのはすなわち、推論の力であり、その力をつけるべく1つずつ勉強を積み上げていくというのが、真の勉強方法であると私は考えています。

私が中学生に国語を教えない理由
中学国語は学校の先生が言った答えが答えだからです。
ようするに暗記なんです。
だから教えない。教えてても楽しくないから。
マジメな話をしましょう。
国語は小学生から大学受験生まで
「次の文章」を読んで「答える」だけの科目です。
しかも答えは問題文に書かれてあります。
書かれているのになぜ点をとれないのか?
文章の構造をもとに「どこに書かれているのか」を
特定する必要がありますが、
それができていないからです。
国語は小学生から大学受験生までボーダレスの科目ですが、
一般的には高校生になってようやっと
構造読解能力が問われます。
本当は小学生が読む小説やエッセイにも構造はあるんですよ。
小説は「論理国語」ではないなんて馬鹿も休み休み言えってなもんです。
しかし日本の学校では小説は感性のもので
読み方は自由と教えます。
で、大学受験する頃になって
小説に「正解」があるのか、と愕然とします。
まあ、日本語の文法に依拠した恣意的な正解であることもありますけど。
というわけで、姿勢を正して構造を読み解きたい人を対象として
私は国語の授業をしています。
一緒に勉強しませんか?

勉強しても「試験の点数が伸びない人」の問題点とは?
現代文、古文、漢文、英語、すなわち「読む」と「書く」の教科は、参考書や問題集の解説を読んで納得してもちっとも力がつきません。したがって点数が伸びません
参考書ルートという言葉が流行っていますが、参考書ルートの問題点はまさにそこにあります。解説を読んで納得したものの、つぎ同じような問題を解いても解けない。もっとひどいケースだと、そもそも参考書の解説が何を言ってるのかわからない・・・・。
「なぜ」を理解する
参考書の解説に書かれてあることに関して、「なぜそのように言えるのか」を理解することがまず重要です。
と、私が言ったところで、おそらく「なぜ」が理解できないので勉強が途中で止まっている、力がつかない、点数が伸びない、ということだろうとお察しします。
そういう時は仕方ないので、家庭教師を雇ってください。なにも宣伝で言っているのではありません。予備校に行こうと竹田塾に行こうと、「なぜ」が理解できない限り、点数は伸びないわけですから、なぜそのように言えるのかを説明してくれる先生を雇うしかありません。
目の前に「ある」文字を読むということ
「なぜ」が理解できない人は、問題演習や模試において、目の前に書かれてある文字を読めていません。このことは毎晩高校生と授業をしていて、しかと実感することです。意味が理解できない言葉や文章を読み飛ばしています。
そんなのありえないことです。関関同立やマーチクラス以上の大学に進学なさりたいのであれば、目の前に書かれている文字をそれとして正確に、読み、理解する必要があります。
「書いてあるものが読めていない」生徒さんは、宿題において解説を丸写ししてきたりします。絶対に力がつきません。何年浪人しようと絶対に合格しません。これだけは保証します。わからないところで「正しくつまずく」こと。そして立ち止まり、なぜそうなっているのかを教員と一緒に理解すること。そのことによって、つぎ同じような問題を解いた時に自力で「再現」することができるようになります。
高校生のみなさん! 「つまずく」ことは良くないことだと思っている人が多いですが、受験に出てくるような文章は、「正しくつまずいてほしい」と著者が思っている箇所が必ずあるのです。著者は「意図的に」読者を「つまずかせている」のです。そこを「飛ばす」からいつまで経っても「読める」ようにならないのです。
正しい勉強法とは
現代文、古文、漢文、英語の勉強法とはしたがって、わからないところで正しく立ち止まり、「なぜ」そうなっているのかを理解し、そのうえで同じような問題を解き、それを再現するというものです。
皆さん、このことはよくご存じでしょう。しかし、それができないから、「それ以外の勉強法はないですか?」と思って「勉強法を教えてください」と言ってるように私には聞こえます。
皆さんが知っている「苦痛を伴う勉強法」が、現代文、古文、漢文、英語の勉強法です。
つまり勉強というものは、より楽をして点を取ろうと思えば思うほど泥沼にはまっていくものなのです。
正解が書いてあるのに得点できない!
最後にちょっとした雑談的な話を。
よく「国語は問題文に正解が書いてあるから満点を狙えます」と言われます。例えば、元東進ハイスクールの出口先生は、そのようにメルマガに書いておられたと記憶しています。
私は出口先生の意見に賛成です。確かに国語は、問題文に正解が書かれてあります。しかし、それでもなお、点が取れない生徒さんが大量にいます。それはなぜかといえば、簡単に言えばどこに正解が書かれてあるかが特定できないからです。
なぜ特定できないのかといえば、文章の構造が読み取れていないからです。構造というのは、それが可視化されれば、矢印やイコールといった、これ以上ないほどに簡単な記号で示すことができます。しかし、問題文にそれらは最初から印刷されていません。したがって、目に見えない矢印やイコール記号を読み解かなくてはなりません。
それができないと入試の現場でパニックになります。これは非常に不幸なことだと言わざるを得ません。例えば、英語は、単語の意味を暗記していない、あるいは忘れたということであれば即アウトというシビアな現状が入試において存在します。
しかし国語は正解が「印刷された問題文」が配られるわけですから、その中に目に見えない矢印とイコール記号を自分で付け加えることができれば満点を取れます。
にもかかわらず、それができないというのは、非常に不幸なことではないかと私は思います。だって、正解を印刷して配ってくれてるんですよ?

国語は感性で解くと失敗します
現代文は感性の教科だから教えられない。中学高校の国語の定期試験は学校の先生が言ったことが正解。こういった誤解を抱いている人が多いのが現状です。
しかし国語は、論理の科目であり、教えることができます。「学校国語」が少々「特殊」なのであって、入試問題は参考書に載っている「正解」を覚えて正解できるものでは決してありません。
論理とは何か
論理とは文章が持つ構造のことです。
よく「論理的に考えなさい」とか「主観を排して読みなさい」などと言われますが、それはすべて、文章が持つ構造を洞察してください、ということを言っています。
そもそも主観を排するなんて脳の構造に逆行するようなことなど、私たちはできるはずがないのです。そうではなくて、問題文が持つ構造を読み解くこと、これを論理的思考といい読解力と言います。
どのように構造をとるのか
問題文の中から言い換え表現と反対表現をとることによって、文章が持つ構造が見えてきます。よく学校の先生が「接続詞に気をつけて読みなさい」とか「接続詞に印をつけなさい」とかと言いますが、それは問題文の中から言い換え表現と反対表現をとるために必要だからです。
私のもとには、「学校の先生の言いつけどおり接続詞に印をつけて読んでいますが、ちっとも国語の成績が上がりません」という人がしばしば訪れますが、彼ら彼女らは、なぜ印をつける必要があるのかを学校の先生から教えられていないのです。
著者の主張の取り方
中学生のうちはまだマシかもしれませんが、高校生にもなると著者の主張が明示されていない論理的文章を読まされます。そういう時はどのように著者の主張をとるのか?
問題文の中から発見した言い換え表現と反対表現をもとに著者の主張を取ります。例えば、倫理と科学が対立構造を成している場合、著者がどちらに重心を置いているのかが分かれば、著者の主張をとることができます。
古文漢文も同じ
以上のことは古文漢文についても言えることです。
古文漢文は中高生が一人で解釈を取れない場所にしばしば傍線が引かれます。「この言葉の意味、学校で教わっていない」とか、「この語は『古文単語 315』に載っていない」とか、そう思って「独自の単語集」を作って覚える方もいらっしゃると思いますが、その勉強法は間違いです。
そういった傍線部というのは、「前後の文脈から推論する」ことによって、単語の意味をとるというのが正攻法の解き方です。
漢文は接続詞が少ないですが、古文はいくつか重要な接続詞があります。この場合の接続詞というのは順接の接続詞であり、逆接の接続詞のことです。それらに依拠して文脈をとっていけば学校で習ってない古文単語が傍線部に含まれていても正解することができます。
生涯つかえる読解テクニック
要するに、「受験用の読み方」というものが存在するということです。しかしそれは決して、くだらない受験のテクニックを意味しません。受験用の読解テクニックというのは、簡単に言えば、推論する能力のことです。文章の構造を明らかにした上で、確実な情報から不確定な情報「X」が何なのかを導き出すことを推論といいます。
それができれば志望校に合格できます。
それどころか、大学においてもさほど困らないはずです。私は理系のことを全く知りませんが、文系においては、大学の課題はたいていレポート課題です。例えば、2000字ほどのレポートを仕上げて期末に提出し、その出来よって成績がつけられます。もちろん授業参画度なども考慮に入れられますが。
あるいは大人になってからも、推論する力は充分使えます。というか、推論する力を使わないといい人生にならないと私は思います。世の中は不確定な情報であふれています。不確定な情報「X」を、確実と言えるであろう情報を元に推論する。そうしないと人に騙されたり、みすみす不幸になる道を選択したりすることになるでしょう。
というわけで、今回はこのへんで話をやめておきます。ともあれ国語は、感性で解くと失敗します。
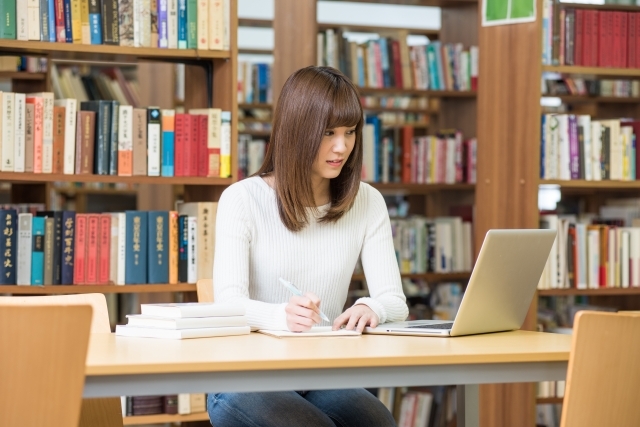
抽象的な論説文対策!現代文の入試問題でよくみる「概念」とはなにか?
抽象的なことが書かれてある文章を読むのが苦手だという人に向けて、今回は「抽象」についてお話したいと思います。
抽象とは「同じ」ということ
抽象は同じということです。例えば、動物という言葉は抽象名詞です。なぜなら、動物という「もの」はこの世に存在しないからです。
「うちの猫」とか「となりのわんこ」のような具体的な生き物は具体です。
他方、「うちの猫」と「となりのわんこ」の共通点、すなわち動物は抽象です。
では、猫と犬とライオンとオランウータンと象とカブトムシと人間を1つの抽象名詞で言い表せばどうなるのか?
例えば、生き物となります。
理性と感性とはなんぞ?
つまり、個別具体的なものの同じところを抽出した結果生まれた言葉が、抽象です
ところで、大学入試に取り上げられる多くの現代文のベースにある概念は、理性と感性の対立です。もちろん理性も感性もともに抽象です。
理性とは、言葉や数字でなんらかを表そうとする脳の作用のことです。これはみんなと共有することができます。1+1=2というのはみんなで共有可能です。
他方、感性とは、言葉や数字で完全に表すことのできないすべてのことです。すなわち私たちの個別具体的な経験のことです。昨日友達とLINEをしていて面白かったけど悲しかった、という個別具体的な経験をいくら他人に説明したところで、そのディテールやニュアンスまでをもあなたと同じように理解してくれる人はいないでしょ? 感覚というのは究極的には他者と交換不可能なものだからです。
安上りかつ近道とは?
大学入試の現代文の問題文は抽象を表すさまざまな言葉が使われています。すなわち具体的なモノやコトを煎じ詰めた結果生まれた、不可算名詞が散りばめられています。
その言葉の意味を機械的に覚えても、あまりいいことはありません。「どのような個別具体的なものたちを寄せ集めた結果生まれた言葉なのか?」が分かれば、やがて抽象的なことを書いてある現代文がすらっと読めるようになります。
こういうのは高校生一人で勉強するには限界があるので、塾や家庭教師に頼ったほうが結果的にお得です。とりわけ早稲田大学の入試問題は、学部生が読むような哲学の入門書や概説書から問題文が引用されています。哲学なんて抽象の塊のようなものですから、哲学を学んだことのある先生、かつ哲学に酔いしれていない先生の教えを乞うた方が、結果的に安上りかつ近道です。
概念に慣れる方法
最後に概念に慣れる方法について言及します。概念に慣れようと思えば、抽象度の高い本をたくさん読むといいというのは誰でも思いつくと思います。しかし、ひとりでそれを読むのが苦痛だったり、そもそもそんなものを読んでる時間がないというのが高校生の実態でしょう。
そういうときは現代文の問題演習の際、問題文の中から言い換え表現と反対表現を取ってください。概念というのは、上の述べたとおり「同じ」ですから、同じことを別の言葉で言い換えています。
また、文章というものはいわゆる仮想敵がないと説得的に書くことができません。例えば「これは白である」ということを主張したい著者は必ず、「黒」を持ち出します。つまり「これを黒と言います。だからこれは白です」というような論法です。したがって、反対表現も文章の中にあります。
というわけで、概念に慣れようと思えば、問題文の中から言い換え表現と反対表現を取る訓練をしてください。
最後に。
現代文が苦手な方は、おそらく現代文の問題演習が後手に回っているはずです。苦手ということは読むのが苦痛ということで、したがって現代文の問題演習をしなくてはいけないとわかっていても、やる気が起きないのであり、折り目すらついてない現代文の問題集が手元に1冊はあると思います。
それはあなたの能力が低いことを意味するのではなく、単純にやる気が起きないということを意味します。やる気を起こそうと思えば、ある程度ものがわかっている先生につくしかありません。
例えば、私は数学が今でも苦手ですが、数学の問題集を解けと言われても、おそらく今日も解かないし、明日も解かないし、あさっても解かないし、来年の今日も解かないと思います。苦手なんですよ。イヤなんですよ。
なので、そういうときは、多少お金がかかっても仕方ないと割り切って親に頼み込んで、ぜひ私の授業を受けてみてください。きっと「いいこと」が待っています。
