ホーム » 合格するブログ » 合格する英語
中学英語でおちこぼれる原因と対処法とは?
簡単に申しますと、英語で落ちこぼれている生徒は、何も英語の能力がないわけではありません。ご存知のとおり、中高一貫校の英語の課題の量は膨大ですから、その膨大な量の「タスク」に溺れているのです。つまり、自分が今何をやるべきなのかがわからない。また、本来「勉強」すべきところが「作業」になってしまっているので、疲れ果てたサラリーマンのようになっているのです。ただそれだけのことです。
中学受験をくぐり抜けて、それなりのレベルの中高一貫校にご入学なさったわけですから、英語ができないなんてことは決してないのです。皆さんそれぞれに、高い能力をお持ちです。
というわけで、私がどのような授業をするのかといえば、まずやるべきことを整理します。中学英語はどこまで行っても、その骨組みはシンプルです。覚えるべき重要構文や文法の知識を覚え、演習を通してそれらを定着させる。長文読解はすらすら音読できるまで練習する。自力で和訳ができるようになるまで和訳をする。試験範囲の英単語を覚える。これだけです。これが中学英語の骨組です。
その骨組みをしっかりと私がフォローしていけば、骨組みに付随する肉に相当する部分、すなわち学校の膨大な課題が意味するところを、生徒たちはおのずと理解して、あるていど機械的に処理できるようになります。
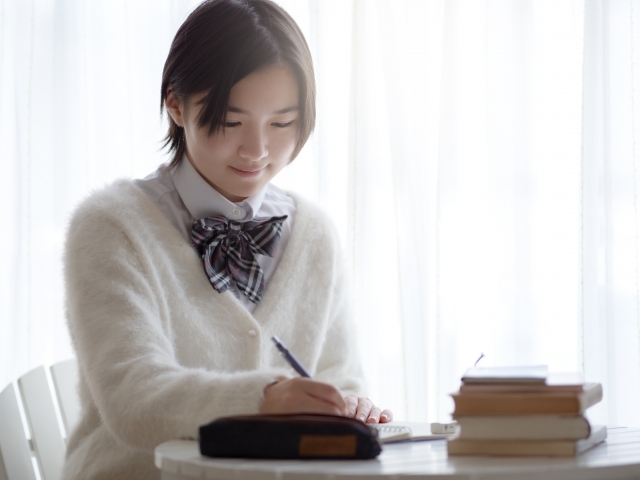
中高一貫校|大学受験対策は何からやるべき?
しかし、大学受験勉強の本質は、自分の行きたい大学のレベルから逆算して勉強の計画を立てるというものです。したがって、中高一貫校の中学3年生が大学受験を視野に入れた時、行きたい大学から逆算して勉強計画を立てることをおすすめします。もちろんその都度、定期試験があるわけですから、その勉強もやりながら、その傍らで自分のための勉強をすることです。
具体的にはまずは、長文読解と英単語です。本当は長文読解演習をバンバンやってほしいのですが、読めない単語が多いと長文を読む気がしないので、長文読解演習と大学受験レベルの英単語の暗記はセットだと思ってください。単語の本は高校に入ると「ターゲット1400」とか1900とか「システム英単語」とかを学校で支給されるでしょうから、それを使えばいいと思います。
問題は長文読解です。英文は前から塊ごとに訳すことが基本です。特に共通試験においては、それができないと確実に時間切れになります。したがって、毎日英文を前から塊ごとに訳す訓練をすること。
次に、文と文の関係、あるいは段落と段落の関係を言えるようにすること。今読んでいる文は前に読んだ文に支えられて、そこに存在しています。マーチ(関関同立)クラス以上の大学を狙える人と狙えない人がいますが、狙える人は文と文の関係や段落と段落の関係をとる能力がある人です。あるいは、その力を訓練によって体得した人です。
私は偏差値40から70を超えるさまざまな大学の過去問を生徒と一緒に解いてきましたが、英文を前から塊ごとに訳せ、かつ文と文、あるいは段落と段落の関係を洞察することができれば、さほど難しい問題はないというのが私の実感です。もちろん、「早稲田の英単語」はエグイですが。
というわけで、文章の構造をとる練習を中学3年生のうちからやってください。それが大学受験英語の本質です。

英語が「まったくできない人」がやるべきこと3つ
しかし、私のように、成績最下位層から成績最上位層の生徒さんまで教え、かつ中高6年間をとおしてやるべき勉強の内容を知っており、かつトップクラスの成績の人たちが何を理解しているのか、がわかっていると、成績最下位層の人が何がわかっていないのか? が見えてきます。
さて、英語がまったくできない人は何をやるべきなのか? について以下にまとめましたので、ご参考になさってください。
1,教科書の音読
英語というのは音=サウンドのメディアです。言葉の字面=スペリングに意味があるのではありません。音=サウンドに意味があります。したがって、まずは音読するしかありません。これは日本語の古文もまったく同じです。古文はもともとは読み聞かせのメディアでしたから、耳で聞いてしっくりくるような言葉の配列になっています。
英語がまったくできない人は頭=理屈で英語をとらえようとしています。しかし、先にも述べたように、英語は音=サウンドに依存する言語ですから、まずは声に出して読みましょう。カタカナ英語でも構いません。英語ができない人は簡単な教科書の文章であっても、単語すらが読めなかったりします。 ownすらなかったりするのです! まずは音読!
2、主語と述語動詞をまず訳す
より厳密に言えば、英文は前から塊ごとに訳すのが鉄則ですが、英語ができない人にそれを言ってもしかたないので、ここでは主語と述語動詞をまず訳そうと書きました。
英語がまったくできない人であっても、主語がどれで、述語動詞がどの単語か、くらいは分っています。しかし、助詞の扱い方がまずい! これが英語ができない人の特徴です。
主語には必ず「は」「が」という助詞を入れます。述語動詞はいいとして、目的語は必ず助詞「を」を入れます。そういったところが英語ができない人はまったく出来ていません。
助詞というのは、学校で助詞だけを教えてくれることはまずありません。しかし、実は英語も現代文も古文も、助詞を適切に運用できるようにならないと文章が読めるようにならないのです。文章というのは「関係」です。その関係を繋ぐ接着剤のようなものが助詞なのです。主語には「は」「が」、目的語には「を」を必ずつけて訳します。
3,文法は誰かに説明してもらう
説明書きが比較的充実している問題集を使うのは言うまでもありません。しかし、それでもわからないことが必ずあるでしょう。例えば中学生だと、be動詞と一般動詞の違いすら理解してない人がいます。そんなものはいくら参考書を読んだところで理解できるはずもなく、「なぜ?」もなにもなく、とにかく「be動詞とはそういうものなのだ」というのを頭からしつこく言われ続けられないとなかなか定着しません。
なぜ is がbe動詞なのかを知りたければ、大学院に行って勉強するしかありません。日本の教育制度はへんなので高校生まではそんなことはやりません。 is はbe動詞です。以上、終わり、です。それで納得できないのであれば、誰か先生について、「これはこういうものなのだ」というのをしつこく教わるしかありません。英語というのは半分以上は文法という法則を「身体に」覚えこませる教科です(日本の場合は)。「なぜそうなっているのか?」というのは大学院に行けば教えてくれます。
いかがでしょうか。まずは音読。次に一文の主語と述語動詞をとる。さらに文法は、「それはそういうものなのだ」というのを、誰かにしつこくに言われ続ける。その3つのことを半年ほど続けていれば、「まったくできない」から「ちょっとはできる」レベルになります。
余談。先生につくのなら、試験に頻出の箇所をよく知っている先生につくといいです。たとえば、英文を見た瞬間に、試験で空欄にされる前置詞が言えるとか、そのレベルの先生を選んだ方が学習効率はいいです。できれば、定期試験で抜かれるのではなく、入試で抜かれる箇所を知っている先生がベターです。そのほうが勉強に無駄がありません。

共通テスト「英語」を時間内に解ききる方法
したがって、文中にある副詞がよく分からなかろうと、名詞の意味が分からなかろうと、第2問の問題文に出てくる学校名が読めなかろうと、そうなことはどうでもよく、とりあえず主語と述語動詞だけを取ってサクサクと前に読み進めることが重要です。
意味の分からない単語が出てくるたびに立ち止まっているから、時間内に解けないのです。
それでは設問が解けないだろうと思うかもしれません。問題の構造を洞察できていないからそういった疑問が生まれます。
問題の設計は「各段落で何を言ってるのか」がとれれば充分答えることができるようになっています。
先に設問を読んでから本文を読むとか、先にノート(サマリー)に目を通してから問題文を読むなどのテクニックは、おそらく皆さん実践しておられると思います。それでも時間切れになってしまう場合、文章の細かなところは捨象し、主語と述語動詞だけを追いかけてみてください。
ちなみに、難関私大の現代文もまったく同じです。早稲田の現代文など、学部生でも理解できない哲学の文章が出てきたりします。哲学の文章は一文がかなり長いし、そもそも普段わたしたちが意識していない概念をテーマとしていますから、普通に読んだのでは理解できません。
したがって、主語と述語だけを追いかけていきます。共通テストの英語もまったく同じです。読まなくていいところ、読めなくていいところに拘泥するから時間切れになるのです。

共テ対策「時間内に解けない!」を解決する方法
1,大問1つをまるまる落とす
共テはなにも満点を取らなくてもかまわない試験です。国公立であれば、自分が志望する大学の正答率が公表されているでしょう。私大も同様に、おおむね何割ぐらいの正答率があればよいのか、データが出ているでしょう。例えば8割であれば、大問1つを落とし、その代わり、手をつけた問題は全て正解できるようにするという対策があります。もちろんこれは、ある程度英語の基礎力がないとできませんが、逆に基礎力があれば充分可能なテクニックです。
2,先にサマリーに目を通す
サマリーは読むのが面倒くさい長文読解問題に何が書かれてあるのかを概説してくれています。それにざっと目を通すだけで、だいたいどんなことが書かれてあるのか、どんな順番で書かれてあるのかが見えてきます。サマリー目を通さないでいきなり問題文を読むから「クマムシ」につまずくのです。
3,英文を前から訳すクセをつける
英語は前から、チャンク(かたまり)ごとに訳します。例えば、主語で切る。動詞で切る。目的語で切る。関係代名詞節をかっこに入れる。前置詞の前で切る。などし、前から読んでいきます。そのクセをつけておかないと共テの問題は時間内に解き切れません。
共テの英語の問題は新課程の問題が導入されて、ほぼ高校生の限界の分量になっています。国語も同じです。私はそのことを決して良いとは思っていません。特に国語など、選択肢を吟味するテクニックを磨けば磨くほど点数が上がるのであって、論理的思考力なんて全く必要のないただの情報処理問題です。しかし、共テを使わないと志望校に合格できないのであれば、どうにか大学側が求める正答率をクリアする必要があります。上記のことを参考に、ぜひ頑張ってください!

英語の長文が読めない人へ「読めるようになる」勉強法とは?
何百人もの生徒さんを見てきてわかることは、英語の長文読解問題が読めない人は、関係代名詞節や不定詞、現在分詞、過去分詞が理解できていないようです。なので、それらをまず「長文読解問題を使って」解説します。
文法書の一問一答のつまらない問題を解く必要がある人は仕方ないので、それを使いますが、大抵の場合、しつこく、長文読解問題を一緒に訳していくうちに身についてきます。
また、高校3年になってもまだ、主語と動詞を特定できないゆえに読めない人もいます。そういう人には主語と動詞の取り方をお教えしますので、一緒に読んでいきましょう。
さらに、目的語は英語でも絶対に「を」という助詞で表しますが(ごはんを食べる、の、を、です)、目的語を表す時に「に」とか「の」という助詞を使って訳す人がいます。そうするととたんに解釈が崩れてきて、その次の文章も訳せなくなって、結局すべてが崩壊します。文脈をとる以前の問題です。このへんは「文法に対する絶対的な信頼を持っているか否か」という「感覚」が、じつは重要になってきます。「読む」って「感覚」にも依拠してるんですねえ。
この感覚を養うには、長文読解の演習量を増やすしかありません。すなわち、読めない人は、これまでたくさん読んでないから読めないのです。私と一緒に読めるようになるまで、たくさん読んでいこう。ひとりで読むわけではないので、苦痛ではないはずです。
たくさん読むコツ
たくさん読もうと思えば、まずは読むことだ。というのは昭和の論法ですが、一面の真理ではあるはずです。しかし、今は令和であって、それを言っても仕方ないので、違うことを話したいと思います。
たくさん読むコツはそれこそたくさんありますが、1つには、同じ文章を何回も読むことです。
例えば、教科書のレッス1からレッスン3はあるていど馴染みがあって「まあまあ読める」ということであれば、レッスン1からレッスン3を毎日5分でいいので音読しよう。
5分でレッスン3の終わりまでたどりつけないでしょうから、何日かに分けてレッスン3の終わりまで音読しましょう。毎日やるのです。1週間も続けていれば、2週間目からはすらすら読めるようになるでしょう。2週間目には音読すれば即座に頭の中に和訳が立ち上がってくるようになるでしょう。
そのようにして、同じ文章を繰り返し音読するのです。そうすると、1カ月もすればレッスン1からレッスン3は完璧に速く読めるようになります。
この「完璧に仕上がったこと」があなたの自信になります。というのは一般的な説明ですが、完璧に仕上がったことがあなたを読めるように「おのずから」導いてくれるのです。言葉というのは100%何らかのロジックでできているものではなく、生活の中からおのずと立ち上がってきたものですから、何かができるようになれば、そのできるようになったことがあなたをさらにできるように導いてくれます。言語の習得というのはそういった不思議な側面があります。
ぜひ、「完璧に出来るもの」を1つ、つくってみてはいかがでしょうか?

英語の長文読解問題を速く読む方法を教えてください
「1分間に130語読めるように頑張ろう」と共通テストの赤本の冒頭に書かれています。どうすれば1分間に130語も読めるようになるのか?
1つには、音読の練習をするしかありません。
共通テストの問題文は、私はさほどいい文章だと思わないので、よそで良問を探し、それを使って、スラスラ読めるまで何回も音読の練習をすることをお勧めします。
例えば、ある生徒さんは北海道大学医学部(総合理系)に向けて勉強していますが、北大の英語はかなり良問ですから、それを使って音読の練習をしています。
2つ目。文章の構造に明るくなろう。
例えば、andという接続詞は中学1年生でも知っている接続詞ですが、長文読解においては「何と何を結ぶandなのか」が即座に理解できないと、とたんに読むスピードが遅くなります。頭の中で「詰まる」からです。
何と何を結ぶandなのかについては、それの特定の仕方が有ります。もう、こんなのはテクニックです。
他にもいろんな対策法がありますが、例えばそういったテクニックを習得することによって、1分間に130語読めるようになるかと思います。
接続詞に着目する
ちなみに、接続詞に着目しながら読むというのも、早く読む方法の1つです。なぜなら早く読めないというのは、頭の中で「何を言ってるのか」がスラスラと理解できず、つまずきつまずき読んでしまっているからです。
頭の中で「何を言っているのか」がスラスラ理解できるというのは、前に読んだ文章と今読んでいる文章の「関係」が理解できるからです。日本語で書かれた文章であっても、英語で書かれた文章であっても、前に読んだ文章と今読んでいる文章と、次に読む文章の「関係」がよくわからないとスラスラと読めないのです。
これは単語の意味が1つ2つ分からなくても、やろうと思えばできるテクニックです。つまり、接続詞に着目しながら読めばいいのです。
例えば、神戸大学の入試問題では必ず、「何を言ってるのやらさっぱりわからない段落(文章)」が現れます。しかし、その段落(文章)の前や後ろには必ず、順接の接続詞か逆接の接続詞が置かれています。
例えば、「がん患者は近年減りつつある」ということを言っている段落の直後に、「しかし」ときたら、がん以外の病気の患者さんが増えていると言っているのか? とか、将来的にはがん患者は増える可能性があると言いたいのか? 要するに、近年がん患者が減っているという情報と正反対のことを言っているということですよね。
という感じで読んでいくことを「推論読み」といいます。多くの高校生は1文の構造をとるのに精一杯だから、頭の中で1文ずつ和訳します。だから、今読んでいる文章と前に読んだ文章の「関係」が全く掴めておらず、その結果、「何を言ってるのか」がよく分からなくなって、徐々に集中力が切れてきてガチャガチャになるのです。
推論読みを意識して、推論読みを習慣化してください。サクサクと読めます。

共通テストの英語の速読ってどうやるの?「最も基本的な勉強法を3つご紹介」
共通テスト(英語)の赤本には「 1分間で130語」読めることを目標に頑張ろう! と書かれてあります。早い話が「速読頑張ってね」ということです。
さて、では、どうすれば速く読めるようになるのか? 以下に、最も一般的な方法を3つご紹介しましょう。
1,英単語を覚える
これは当たり前ですよね。単語の意味がわからないとそこで読みが詰まるわけですから。
まず単語を覚えよう。「ターゲット1900」でも何でもいいので、1冊仕上げましょう。
2,何と何を結ぶ「and」なのかを理解する訓練をする
学校の英語の授業や、自分で長文読解の問題集を解いている時、設問が解けたからOKではダメです。問題文の「隅々まで」理解することが「本当の」勉強です。とくに関関同立MARCHに合格したければそういう勉強をすべきです。
さて、速読において重要なのは、「and」です。何と何を結ぶand なのかが即座に取れないと、そこで読みが詰まって1分に130語も読めなくなります。
何と何を結ぶandなのかを毎日意識して読解演習をしましょう。
3,スラッシュリーディング
英文を前から「かたまりで」捉えつつ読むことをスラッシュリーディングと言いますよね。
速く読もうと思えば、一文を最後まで読んで、また前に戻って悠長に訳すなんてことはできません。読んだそばから頭の中に和訳が立ち上がってくる状態にするしかありません(英語を英語のまま理解できればなおいいわけですが)。
たとえば、
その本は/リサが脇に抱えている/出版された/1980年に/イギリスで
という感じで読むわけですが、まあ意味はとれますよね?
スラッシュリーディングの訓練は、東進などの予備校がいい問題集を出していますので、それで勉強なさるといいと思います。
(おまけ)修飾ことばに慣れよう
以上、3つの方法について言及しました。以下はおまけです。
装飾ことば、すなわち関係代名詞節や分詞などに慣れましょうというお話です。
英文はスラッシュリーディングができればさほど読解に困ることはありません。本音を申せば、共通テストの英語のように1分間に130語読みましょうというのはちょっとやり過ぎではないかと思いますが、それでもまあ、スラッシュリーディングで読んでいけばさほど困ることはありません。
ただし、私が授業をしてきた中で感じるのは、修飾ことば、すなわち関係代名詞節や分詞のところで立ち止まってしまって、時間を食っているケースが多いということです。
関係代名詞節や分詞というのは、すぐ直前の名詞を単に修飾しているだけですから、文章の大意を取ろうと思えば、極端に言えば読まなくてもいいものです。
たとえば、「去年までおじいちゃんが持っていた本を私はもらった」という文章の場合、文章の骨組みは「私は もらった」であり、何をもらったかこといえば本です。「去年までおじいちゃんが持っていた」というのは関係代名詞や分詞を使って後からくっつけられている言葉であり、それを端折って読んでも大きく困ることはありません。もちろん選択肢問題で端折った箇所が出てくる可能性は充分にありますが、とりあえず急いで思うと思えば、関係代名詞節はさらっと読んでしまえばいいのです。
が、すぐ直前の名詞を修飾しているだけというのがうまく理解できない生徒さんがなぜか多い。これが私の知っている実態です。だからといって、文法の問題集をやってもさほど読めるようにはならないもので、こういうのは日々少しずつ長文読解演習を行いながら慣れていくのがベターではないかと思います。慣れてしまえば、スラッシュリーディングがサクサクできるようになる生徒さんが多いです。
